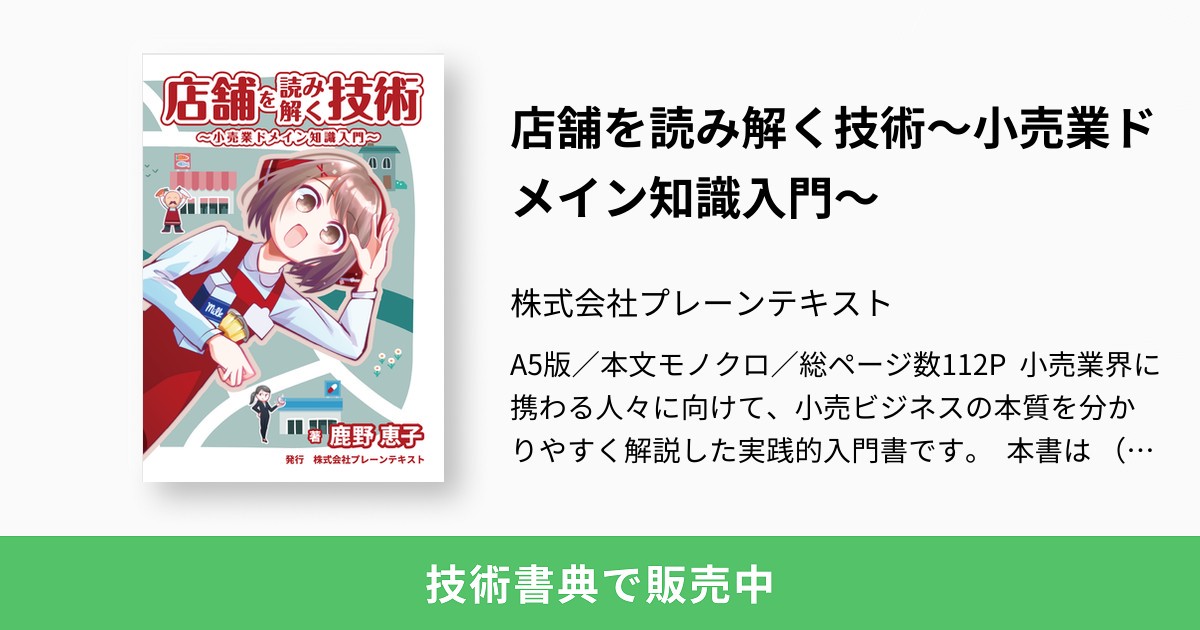2024年11月に開催された技術系同人誌即売イベント 技術書典17 で「店舗を読み解く技術~小売業ドメイン知識入門~」という同人誌を発売しました。
技術書典17会期中(~2024年11月17日)のご購入はこちらから!
店舗を読み解く技術~小売業ドメイン知識入門~:株式会社プレーンテキスト
A5版/本文モノクロ/総ページ数112P 小売業界に携わる人々に向けて、小売ビジネスの本質を分かりやすく解説した実践的入門書です。 本書は (1)業界の歴史と最新トレンド (2)店舗の読み解き方 (3)数字の読み解き方 という3つの切り口で、業界誌のライター兼編集者が、「わかりにくい」「とっつきにくい」といわれがちな小売業の世界を案内します。 図表やデータを豊富に収録し、ドメイン知識とその「さらに前」の「業界の常識」や「大前提」「暗黙の了解」を丁寧に解説。小売業界特有の課題や要件を理解し、より効果的なソリューションを提案・開発したい人々にとって、必携の一冊です。 ■本書のゴール • 小売業の歴史や知っておきたい常識をコンパクトに学べます • 店舗を見て言語化するための前提知識を身に着けることができます • 店舗に関する数字の基礎知識を理解することができます ■想定する読者層 本書は、以下の方に向けて書かれています。 • 小売業で働いている方、働くことを検討している方 • 小売業に関わるIT エンジニアの方 • 小売業に商品を提供するメーカーや卸売業の方 ※本書において「小売業」とは、複数店舗を展開するチェーンストアを主な対象としていますが、中小規模の小売業にもほぼ適用できるように配慮しています。 ーーー 小売業は店舗という接点が街に開かれているところが大きな特徴です。観察することで、その企業が向かおうとしているところを読み解くことができます。筆者は記事執筆のために数百の店舗を見て、記録し、言語化する技術を身に着けてきました。地図を得て、店舗を読み解く技術を得ることで、小売業界を楽しく旅することができるのではないかと筆者は考えています。 小売業は、人と商品とお金と社会の接点で、人間臭くてとっても面白い業界です。小売業の面白さを、小売業でお仕事を始めたばかりの方はもちろん、小売業に関わるエンジニアさん、メーカーの方、関連するすべての方に伝えていきたい。そんな思いで本書を世に送り出します。
techbookfest.org
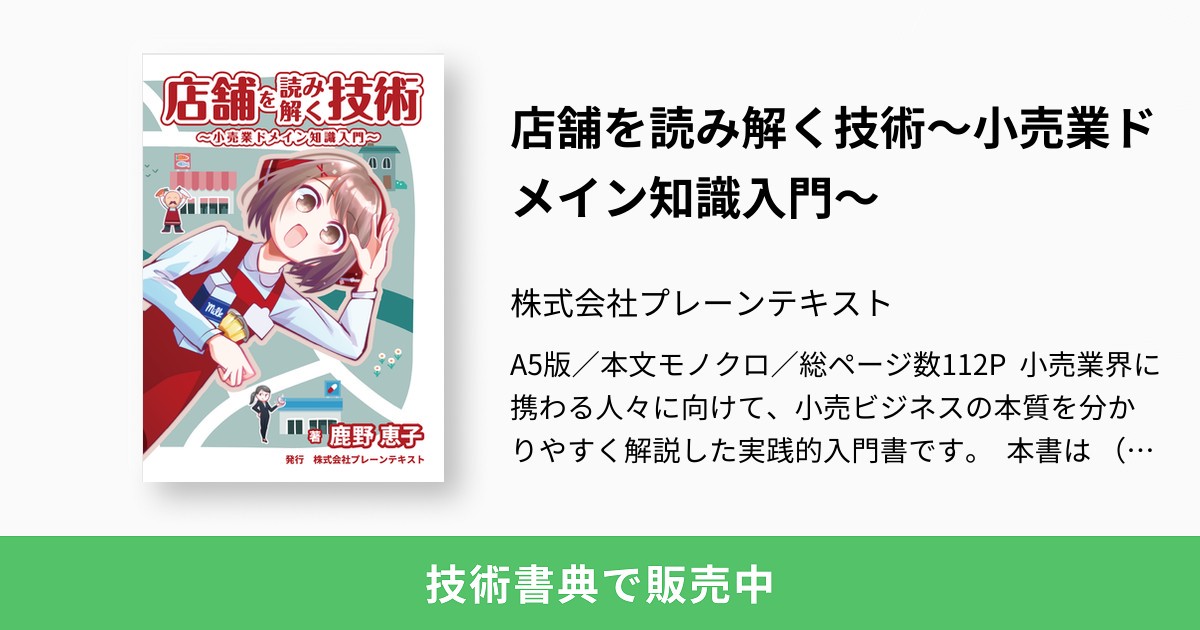
仕事と育児と親の世話を並行でしつつ、なんとか当日までたどり着きました。HPはゼロ寸前、瀕死状態の筆者なのですが、ここまでの道のりを振り返ります!
目次
- 目次
- プロジェクト開始のきっかけ
- 執筆のモチベ維持はAwasome Habitsを使用
- 執筆環境
- 組版はRe:Viewで
- 校正はPDFと紙で3回
- 楽しく進んだ表紙デザイン
- 値付けなど
- 印刷はプリントパックで
- 告知はXにて
- そしていよいよイベント当日
- 託児も利用させていただきました
- この先
プロジェクト開始のきっかけ
私は普段小売業関係の業界誌で編集記者をしつつ、自社でIT企業さんのマーケティング支援などの仕事を受託しております。せっかくさまざまな知見を積み重ねてきたのに、それをまとめて誰かに伝えるということができずもったいないな…と感じていました。
そんな折、今年の春、久々に遊びに行ったのが技術書典16。そこで楽しげな雰囲気になんとなく「ここに次回は出展したいなー。と思ったのが運の尽き。
技術書典、前回出典したのは2018年10月の技術書典5でした。当時法林浩之さんと一緒にやっていたPodcastの宣伝を兼ねてVimとEmacsのメモ帳を売りさばいたりしていたようです。

本業は原稿を1本書いていくら、という仕事が多いもので(さらに無記名の広告案件も多い)、いかに自分の原稿をストックしていくか、という課題感を抱えていました。
商業出版にも憧れはあるのですが、やりたいのは小売業というニッチな分野。初版3,000部を印刷して全国津々浦々に配本する方法では自分の作りたい本をつくるのは厳しいだろうな……、とうすうす感じていました(筆者のキャリアのスタートは版元の取次営業でしたので、内容と部数のバランスにはうっすら土地勘があります)。
であれば、自分が版元になって出版すればええやん!と気づいたわけです。リスクも対価も自分のもの。誰にも迷惑をかけず作りたい本が作れる。ほな一度やってみよっか、となりました。
執筆のモチベ維持はAwasome Habitsを使用
一番難しいのは執筆に対するモチベーションを維持し続けることでした。普段「1本いくら」という原稿を書いているわけですから。本書の執筆時間は無給なので、推進力は自分の中から湧き上がるモチベーションしかありませんし、書いたところで売れるかどうかもわかりません。なるほど先人の書籍の著者さんたちは、そのようなところを乗り越えて、本を作っていたのか…。
筆者は書籍執筆でも資格取得の勉強でも、マラソンの練習でも、何か習慣的に継続したいときは、基本的に朝早起きして対応するタイプ。
今回も「一日◯分」と決めて、粛々と書き続けました。Awasome Habits というアプリで毎日の作業を記録して、Xにポストすることでモチベーションを維持。(やたらこのアプリに対する関心が高かった…)
Awesome Habits – Habit tracker for iPhone, iPad, Mac and Apple Watch
Instead of setting goals, start improving your regular habits. Small and easy changes will compound into remarkable results. With our app, you will get better every day and achieve the kind of success that lasts.
www.awesome-habits.com
この #技術書典への道 というポストをさかのぼると、夏休み~娘息子自分体調不良という時期などが思い出され、幼児をかかえた執筆はほんと大変だったなぁ…と遠い目になります…。
執筆環境
執筆のアプリは前作(リアル店舗は消えるのか)に引き続いてScrivenerを使用しています。私は複数拠点にPCを置いて仕事をしているのですが、Dropboxで原稿を同期して、どこでも同じ状況で書けるのはとても便利。
Scrivener - Literature & Latte
Typewriter. Ring-binder. Scrapbook. Scrivener combines all the tools you need to craft your first draft, from nascent notion to final full stop.
www.literatureandlatte.com

Scrivener、「考えながら書く」には最適なツールだと思います。iPadで読み込むとレイアウトなどが崩れてしまうので、そこだけ解消されれば私にとっては最強のツールになりそうなのですが。
目次をざざっと作り、小見出しごとにファイルを作って書き進めます。順番の入れ替えなどは自由にできますので、柔軟に製作することができました。
組版はRe:Viewで
版組はプロジェクトスタート初期にRe:Viewを使うと決めていました。これが本当に素晴らしいツールで。私はWSLにUbuntuを入れ、Dockerで動かすというような形をとりました。お恥ずかしい話、仕組みがどうなっているのかしっかりと現時点で把握できていないのですが、なんとか動いていて、PDFを出力できるから問題ないと思っています。
Re:VIEW - Digital Publishing System for Books and eBooks
Re:VIEWは電子書籍と紙書籍のための、簡潔かつ強力なデジタル出版ツールです。コンピュータ書等の技術書籍(紙・電子)の商業出版や同人出版に利用されています。
reviewml.org
Re:Viewのすばらしさは、本を出すときに本文を書く次に難易度の高い(と筆者が考えている)誌面のレイアウトの部分をまるっとお任せできるというところだと思います。あまり難しいことを考えずに文章を書いて、実行すれば、美しい版組の誌面が出来上がる。しかも無料…。簡単なものであれば版面をWordで作ったりもするんですが、いろいろとイマイチと感じていた私にとってRe:Viewとの出会いは福音でした。(記法は覚える必要がありますがそれほど難しくはありません)
図版はAdobe Illustrater で作りましたが、思っていた以上に工数を食いました。自分の得意分野が図解なので、もっと図解したかったんだけど、これはスピードが追い付かないと断念。
最終的にはScrivenerで執筆した原稿を、えいやっとプレーンテキストで出力して、Re:View形式に書き換え、PDFに出力。調整して出力し直しなおすことを何回も繰り返しました。
校正はPDFと紙で3回
校正は普段の仕事にのっとり大きく3回行いました。初校は紙で、再校はPDF、三校は紙で行っています。
校正を行う際には、自分の視点を変えてみることが大切です。そして視点を変えるためには、違ったアウトプットの形式で見るという方法が効果的です。(視点を変えるためのもう一つの方法は、しばらく時間をおいてから読むことなのですが、これは校正にある程度の時間を取れるということが前提になっていて今回のケースには適しませんでした)
PDFで校正を行う際には、iPadアプリのGoodnotes にPDFを読み込んで、Apple Pencilで赤字を入れています。これは普段のお仕事通りで非常にやりやすい方法です。
Goodnotes|生まれ変わったノート|メモアプリ
世界中の何百人もの人々に愛されているAIノートアプリ、Goodnotesを使ってみよう。
www.goodnotes.com

本業では紙の本を作っているのですが、今回の同人誌制作で校正者の方を通さなかったのは本当に苦渋の決断でした。次回は校正とレビューは絶対入れる!と誓います(そのためには前倒しの制作が重要なわけですが…)。
それと、地味に自分が入れた赤字をデータ上で修正する作業がなかなか大変でした。これを毎回本業ではほかの人にやっていただいているんだなぁと思うとともに、人に一回預けることで生まれた時間的な余裕が、「新たな視点でゲラに向き合う」ことにつながっていくのね、とも改めて感じました。
楽しく進んだ表紙デザイン
9月に入ってから、表紙をどうしようかと考え、技術周りにも理解がある 藤木まなさんにお願いすることにしました。即レスでポンポンとお話が進んでいきます。やり取りの中で、もともと親交がある漫画家の湊川あいさんにイラストを依頼するのはどうかという方向になり、ご相談差し上げたところ快諾…!クオリティの高い仕事をスピーディーに進めてくれるお二人にぐいぐいひっぱっていただいて楽しく表紙を製作することができました!
湊川さんのイラストを採用させていただくことで、オフラインイベントの会場でかなりたくさんの方が関心を持って表紙を見てくださいました。アイキャッチ効果すごすぎです。(一部の方には湊川さんの新刊と勘違いさせてしまったのかも…)
値付けなど
イベントで売るから区切りのいい金額でとは思っていたのですが、薄い本に2000円というのはちょっと抵抗がありました。しかし内容についてはそれなりに自信があり、安く広く頒布するのもあかんだろうと思ってぐっと腹に力を入れて2000円と値付けしました。
仕上がってきた紙の本はそれなりの束の厚さを感じるものではあったので、この値段でもアリかもと感じましたが、ちゃんとそれだけの価値を提供できているかについては、祈るような思いです。値付けマジ難しい。
この値段は間違ってはいなかったと思いますが、薄い本を1000円で売るというモデルの方が、同人誌即売会という場にはフィットし、初見の方は手に取りやすいのでしょう。今後はそのような本も作ってみたいと考えています。
印刷はプリントパックで
印刷はプリントパックさんにお願いしました。ここ10年ぐらい大量の刷り物はこちらにお願いしています。安いし早い。オンラインできっちり完結する潔さが好きです。紙は事前にサンプルを取り寄せて、選定しました。
表紙は4色印刷 マットコート220kg、本文は上質紙90kgというとてもスタンダードな組み合わせ…だと思います。
バックアップ印刷所の日光印刷さんやねこのしっぽさんも検討したのですが、同人誌独特の仕様のわかりづらさがあり、今回は見送りました。でも会場で各スペースの机の下まで搬入してくださっている様子をみて、「これは便利すぎるだろ」となりました(宅急便で会場まで本を届けた出店者は、荷捌き所まで自分で台車を使ってアイテムを取りに行く必要がありました。台車を戻さなければならず、2往復する必要があり、会場の端っこにスペースがあった弊社にとっては、とてもいい運動になりました…)
あ、そうそう。プリントパックさんにも落とし穴が一つありました。プリントパックさんはPDFを製作したアプリについてかなり細かく確認が入るのですが、その選択肢一覧にRe:Viewはありませんでした。ギリギリで入稿しようとしたときにそれに気づいて真っ青になったのですが、しれっとそのまま入稿してしまいました。うまく出力されたのでよかったのですが、これはあんまりにリスキーなので他の方には推奨できません…次回までに確認をしておこうと思います。
告知はXにて
主にXを使って告知をしまくりました。関係者の方にもたくさんリポストをいただいて、imp1万を超えるポストも。ありがたすぎます。
mochikoastechさんのこちらの本をとーーーっても参考にさせていただきました。学ぶことが多すぎでした…。
届ける工夫 ~欲しい誰かに見つけてもらえる60の方法~
72ページ / A5サイズ / 電子版はPDF(フルカラー) / 紙の本は表紙カラー、本文モノクロ 技術書典15(2023年11月11日~26日)の新刊「届ける工夫 ~欲しい人に知ってもらえる60の方法~」です。 「PDF版」は名前のとおり、PDFをダウンロードできます。紙の本はついてこないので注意してください。 紙の本は完売してしまいました。2024年6月時点での再販時期は未定です。 紙で欲しい方は「入荷お知らせメールを受け取る」を押しておくと、入荷されたときにメールが届きます。 PDF版は技術書典オンラインマーケットでも購入可能です。 https://techbookfest.org/product/47ALwiX8uAUTzZifisvYmD 「ダウンロードカード用」は、既に紙の書籍をお持ちの方向けのファイルです。紙の書籍を購入された方は、あとがきの後ろにダウンロード用のパスワードが記載されています。ダウンロード後、ダウンロードカードまたはあとがきに記載されているパスワードでZIPファイルを解凍してください。パスワードをご存じでなければ、「ダウンロードカード用」のZIPファイルをダウンロードしても電子書籍(PDF)を読むことは出来ませんのでご注意ください。 --- 本書には、私が技術書典で本を出すとき実際にやっていることを元にして、あなたが「もっとたくさんの人に手に取ってもらって、○○の良さを知って欲しい」と思ったらこういうことをするといいですよ、という工夫をぎゅぎゅっと詰め込みました。題材は技術書典ですが、それぞれの工夫は汎用的なものなので、たとえば同人誌即売会で自作の小説を売っている人や、ハンドメイドのアクセサリーをマルシェで売っている人など、自分の作ったものを自分で販売している人にはきっと共通して参考になる内容だと信じています。 第1章から第6章まではやるべきことが時系列で並んでいるので、通して読むと一通りの流れが把握できます。あとはイベントの開催直前になったら「第4章 イベント開催前の工夫」を読み返してみる、というように、「いまの時期には何をすべきか」の参考にするのもいいでしょう。 販売部数という数字を積極的に追い求めることを、拝金主義のように感じてしまう人もいると思います。また、謙虚さゆえに、自著の告知や宣伝を控えめにしている著者も多いと思います。ですが「販売部数」の向こう側には、その本を手に取って、価値を感じ、お金を払って買ってくれたひとりひとりが居ます。必要としている人の元まで届いて欲しいという気持ちで頑張って告知すること、そして届いた結果の数字を喜ぶこと、果たしてそこにネガティブな要素はあるのでしょうか?それに読者の立場で思い返してみると「こんな本あったの?早く言ってほしかった!あー、もっと前にこれを知っていたら……!」という気持ちにはきっと覚えがあるはずです。 流れていく情報の量が多い現代において、困りごとで調べ物をしたときに「まさにこれが知りたかった!」という情報に辿り着くのは至難の業です。良いものを作れば黙っていても見つけてもらえる、という時代ではないのです。必要としてくれているどこかの誰かにあなたの本を届けるには、ちゃんと見つけてもらうための情報発信が必要です。 本書には、欲しい人に存在を知ってもらい、手に取ってもらうための実践的な工夫が詰め込まれています。「せっかく書いた良い技術書が、存在自体を知ってもらえていないせいで売れていない。この本を必要としてる人はたくさん居るはずなのになんで届かないんだ……」という悔しい思いをしたことがある著者の方にとって、きっと役に立つヒントが得られるはずです。 価値のないものを無理矢理売るための広告や宣伝ではなく、折角の良書を「必要としている誰か」へちゃんと届けるための工夫を少しずつ試してみませんか? ▼想定する読者層 本書は、こんな人に向けて書かれています。 * 技術書典の出展サークル * 技術書の著者や編集者 * 必要としている誰かに本を届けたい人 * 本が思っていたより売れず「爆死…!」となったことがある人 * 本があんまり売れずに悩んでいる人 * 宣伝や告知のコツが知りたい人 * 人に見つけてもらえる上手な情報発信がしたい人 * 自分の作ったものを自分で販売している人 * 作ったものの存在や良さをつたえたい人 ▼マッチしない読者層 本書は、こんな人が読むと恐らく「not for meだった…(私向けじゃなかった)」となります。 * 本を書くのは好きだが、書いた本が読まれるか読まれないかには興味がない人 * 販売部数なんか気にせず心の赴くまま技術同人誌を作りたい人 ▼本書のゴール 本書を読み終わると、このような状態になっています。 * 「欲しい」と思っている層に本を届けるための方法を知っている * 存在に気付いてもらうための情報発信の仕方が分かっている * 「宣伝」や「告知」に対して前向きになっている * 以前よりも本がたくさん売れる(具体的な効能効果、販売部数、および安全性を保証するものではありません) ▼実際に読んだ人の感想コメント ▽LINEヤフー DevRel 佐藤 祥子さん 自らの創作物を世に広めたい全ての人にとっての必読書です!72ページの中にイベント出展から告知の技術まで、実践的な販売促進の秘訣が凝縮されています。そして販売数を追求することの本質的な価値を解き明かします。自著の告知に躊躇している著者も、この本を読めば「必要としている誰か」へ自信を持って作品を届ける勇気と方法を得られるでしょう。この本があったからこそ「技術カンファレンスのマスターガイド:企画から運営までの完全手引き」のPR活動をスムーズに進めることができました。技術書典だけでなく、あらゆる作品を持つクリエイターにとっての実用書と言えます。 ▽小説家 朱野 帰子さん(『わたし、定時で帰ります。』『対岸の家事』など) 売れるために必死になるなんて。そんな気持ちは商業作家にもあるはず。でも多くの読者に届けたいなら「本に魅力があれば告知ツイートを1つすれば"届く"はず」なんてドリームは捨てて、読者がほしい情報を得られるよう当たり前のことをやっていこう! と教えてくれる本です。だけど、この「当たり前」の仕事をきちんとできる人って意外といないんだよなー! でも大丈夫、この本さえ読めば!商業同人関係なく作家なら誰もが1冊持つべき本だと感じました。
mochikoastech.booth.pm

そしていよいよイベント当日
いよいよ迎えた11/3、オフラインイベント当日です。
1人でブースに居続けるのは厳しいと感じ、ライター仲間の宮原さんにサポートをお願いしました。販売する本は宅配便で事前搬入。本はやっぱり重い!送料はそれなりにかかりました。持ち帰りたくない…。(ちなみに搬出の情報を事前に見つけられず、みんな売り切るのかとガクブルしていました。イベント当日に「着払い伝票で宅急便搬出可能」という情報を知り、ほっとした次第です)
それと車での搬入も検討していたので「車→台車」で搬入のルートも気になりましたがこれもぱっと見案内がなかったようなので、推奨されていなかったのかもしれません。(会場によって台車利用OK/NGとかあるように思います)このあたりは大規模イベントを運営していた身として、どうしても気になってしまいがちなポイントです。
ブースの位置は一番はじっこ!後ろが壁で非常に広くてありがたかったのですが、同時に入口からは最も離れていたため、トイレに行くたび歩数を稼ぐことになりました。トイレが近いミドフォーです。
「あの布」の技術書典バージョンが欲しかったので「はじめてセット」も頂戴しました。布はかわいいし、ペンも助かる…。存分に活用させていただきました。セットじゃなくて、「見本」カードだけでも販売してくれないかな…。

開場中はゆるゆるとお客さんが絶えず訪れてくださって、本当によい塩梅の雰囲気でした。直接お客様が本を読んで、購入してくださるのはもう字書きをしている僥倖という感じでした。
なにせ、普段の受託のライティング仕事はクライアント様に向けて仕事をしていますから、その記事の評価はよくも悪くもクライアント様どまりなわけです。
実際にどれだけ読まれたのか、あるいは受注につながったのかなどは、我々は関与しません。雑誌の仕事の場合も、たくさんの記事の中の一本を担当するわけで、自分の記事が購読につながっているのかどうかというのは正直なところ誰にもわからないわけです。
書く仕事は面白いのですが、それに対する評価という意味では、もやもやしていたところに、一筋の蜘蛛の糸が垂れてきたように思いました。
イベント会場で目の前で手に取っていただき、感想までもらえる。さらに直接お買い求めまでいただける…。長らく文章を書く仕事をしていますが、このような機会はほとんどありませんでした。「リアル店舗は消えるのか」なんて本を出していますがこの場に来て、「消えるわけないwww!」と強く感じた次第です。
ときに2冊用意した見本誌が足りなくなって、売り物の本をご覧いただいた場面も。(見本誌は4冊ぐらいは用意したほうが良かったかな)
イベント開催時間中は久しぶりの方やそうでない方も含めて、いろいろお話ができたのがとても楽しかったです。自分の本業に関するアウトプットをテックな場ではほとんどしていなかったのですが、そういうものをテックなお友達にお伝えできたのもうれしいことだなと思いました。
あまりブースから離れたくない!という気持ちが強かったこともあって、会場を回ることができず、ご挨拶ができなかったかたもたくさんいました…。隙間でちょっと見て歩いたのですが、それでこれだけ買ってしまったので、あまり会場は回れなくて正解だったのかも。
また、オフラインイベントと関係なく、オンラインマーケットでも本が売れ続けていること(今も)にちょっと驚いています。ぽつぽつとではありますが、販売し続けてくれているのがありがたすぎです。
託児も利用させていただきました
まもなく2歳になる息子のぽこ太郎を技術書典の運営さんが提供してくださっている「にじいろポッケ」さんの託児に預けました。遊んでいる様子がXでポストされていて、親も安心。預け入れと引き取り、すべて夫に任せたのですが、預入の際の質問事項などもすごく的確、スピーディーだったとのこと。ぽこ太郎も新しいおもちゃでたくさん遊べて満喫していたようです。神のように手厚い運営…!!
2024年11月3日の託児の様子
技術書典17のための託児/お子様6名、スタッフ3名
min.togetter.com

この先
積み残し課題としては、まだ見本誌をお送りできていないので早々に送付します!!!!
今回の本で書ききれなかったところもたくさんあるので、次回作(たぶんPOS編とか物流編、マーケティング編とかさらにニッチな話にはなるのですが…)にも挑戦したいと考えています。
あと複数人が寄稿する形式の雑誌も作ってみたいなあ…。夢は広がります。
コミケやおもしろ同人誌バザール、文芸フリマなど、同人誌即売会的なものは他にもいろいろありますので、親和性が高いものに挑戦するのもありかなと思います。
技術書典の会期が終了したら、boothで販売する予定です。
普段の仕事にもフィードバックできる学びも多分にありました。そもそも本を書くこと自体が知識の整理と確認に大いに役立ちます。さらに、ライティングだけに注力できる環境はすごいことだなと痛感しました。今回も、たぶん本づくりにかかる大変さもありましたが、製作、販売、販売促進に関わる工数も非常に多く、これが書籍の印税が高くても10%程度たる所以か…と感じた次第です。
株式会社プレーンテキストとしても、今後の業態を考える一つのきっかけになりそうなイベントでした。関係者の方、支えてくださった皆さんに深い感謝を申し上げます!!!
購入報告と感想をまとめました。
「店舗を読み解く技術~小売業ドメイン知識入門~」購入報告と感想をまとめてみました
株式会社プレーンテキストの技術同人誌「店舗を読み解く技術~小売業ドメイン知識入門~のまとめです。
togetter.com

技術書典17会期中(~2024年11月17日)のご購入はこちらから!
店舗を読み解く技術~小売業ドメイン知識入門~:株式会社プレーンテキスト
A5版/本文モノクロ/総ページ数112P 小売業界に携わる人々に向けて、小売ビジネスの本質を分かりやすく解説した実践的入門書です。 本書は (1)業界の歴史と最新トレンド (2)店舗の読み解き方 (3)数字の読み解き方 という3つの切り口で、業界誌のライター兼編集者が、「わかりにくい」「とっつきにくい」といわれがちな小売業の世界を案内します。 図表やデータを豊富に収録し、ドメイン知識とその「さらに前」の「業界の常識」や「大前提」「暗黙の了解」を丁寧に解説。小売業界特有の課題や要件を理解し、より効果的なソリューションを提案・開発したい人々にとって、必携の一冊です。 ■本書のゴール • 小売業の歴史や知っておきたい常識をコンパクトに学べます • 店舗を見て言語化するための前提知識を身に着けることができます • 店舗に関する数字の基礎知識を理解することができます ■想定する読者層 本書は、以下の方に向けて書かれています。 • 小売業で働いている方、働くことを検討している方 • 小売業に関わるIT エンジニアの方 • 小売業に商品を提供するメーカーや卸売業の方 ※本書において「小売業」とは、複数店舗を展開するチェーンストアを主な対象としていますが、中小規模の小売業にもほぼ適用できるように配慮しています。 ーーー 小売業は店舗という接点が街に開かれているところが大きな特徴です。観察することで、その企業が向かおうとしているところを読み解くことができます。筆者は記事執筆のために数百の店舗を見て、記録し、言語化する技術を身に着けてきました。地図を得て、店舗を読み解く技術を得ることで、小売業界を楽しく旅することができるのではないかと筆者は考えています。 小売業は、人と商品とお金と社会の接点で、人間臭くてとっても面白い業界です。小売業の面白さを、小売業でお仕事を始めたばかりの方はもちろん、小売業に関わるエンジニアさん、メーカーの方、関連するすべての方に伝えていきたい。そんな思いで本書を世に送り出します。
techbookfest.org